
野球を始めたのは小学4年から。当時、男の子は野球をするのが当たり前の時代だった。
周囲を山あいに囲まれた八幡平地区。夏は野球、冬はスキーがお決まりのパターンだった。そんな土壌が奏功し、幼いころから足腰は鍛えられた。
安保が八幡平中へ進学してからは、右サイドスローの好投手として注目された。「このころは、秋田商で同期の高山郁夫(西武―広島―ダイエー)よりも、実績は上だった」(笑)。
中学時代、大館商(現・大館国際情報学院)に故・三浦第三が在職、その後、三浦は母校・秋田商へ転任したことから、安保は三浦の背中を追うように秋田商の門をたたいた。
その理由を、「(甲子園に出場するためには)中央地区の高校に入学することが近道」と思ったことと、秋田商への印象として、かつて、武藤一邦(ロッテ)らが率いた四藤(よんとう)打線のイメージが脳裏にこびりついていたことが、選択理由だった。

入学式直後、硬式野球部への入部者が集まった。50名ほどいただろうか。中学時代は強豪チームのメンバーばかりだった。主将、エース、4番打者…。その顔触れに驚いた。練習は体力づくりがメーンで、本当に厳しかった。日に日に脱落者が出てくる。安保はそんな中、「八幡平には帰るものか」と、歯を食いしばって、耐えた。
その頑張りの甲斐(かい)あってか、1年秋には頭角を現し、全県優勝。2年夏の県大会決勝では、高山、安保の2枚看板で大館商を下し、甲子園出場を果たした。
甲子園では初戦で古豪・広島商と対戦。2-5で敗れたとはいえ、翌年のセンバツ、そして夏の選手権に向けて、高山―安保の2枚看板で乗り切るめどはついた。新チームでは安保が主将で背番号は「1」。高山は「11」。
春のセンバツの重要な資料となる秋の東北大会。秋田商は決勝に進出した。その試合、高山―安保のリレーで東北打線を7安打に抑えたものの、試合は2-4で敗退した。が、甲子園への切符が届いた。
翌春のセンバツの初戦は、高山の140キロ台の速球がさえて、鹿児島商工に6-1と快勝。2回戦の静岡戦は安保が先発、初回にいきなり3ランを被弾した。しかし、急きょリリーフした高山が好投し、延長10回の末、9-3で8強進出を果たした。 準々決勝の相手は帝京(東東京)だった。2年生エース・伊東昭光(ヤクルト)に対して、秋商打線は帝京を上回る8安打を放ったものの、ここ一番でのタイムリーが不発に終わり、0-2で敗れた。背番号「11」のエース・高山の好投も、報われることはなかったが、プロ注目の投手に成長したことを十分すぎるほど、アピールした試合だった。
一方の安保といえば、今だからいえるが、3ランを浴びた静岡戦との試合では肋間(ろっかん)神経痛がひどく、まともな投球ができないほどの状態。1球投げるたびに顔をゆがめるほどだった。結局、初回、1死も取ることもなく降板した。
「チームには本当に迷惑をかけた。今でも悔やまれる」と当時を振り返る。

安保、最後の夏――。県大会は、大半の試合を高山がマウンドへ上がった。安保の状態は、腰痛で投球できる状態ではなかった。
チームは決勝で延長の末、能代を破り、3季連続の夢舞台への出場を決めた。安保は秋田大会での登板はなかったとはいえ、主将として、また1塁コーチャーとしてチームを、そして選手を叱咤激励した。
「恐らく、三浦監督でなければ、ベンチ入りもできなかっただろう」と述懐する。
そして甲子園―。田川(福岡)には辛勝したが、2回戦の瀬田工(滋賀)に0-3で完敗、安保の夏が終わった。
聖地・甲子園の印象を「大きくて、普段の野球ができないほど気持ちが高まる場所だった」という。これから甲子園を目指す球児には、「(甲子園では)自分たちがやってきたことを信じて、プレーしてほしい」というアドバイスを送る。
夏、春、夏と3季連続して出場した甲子園のエピソードを紹介しよう。
2年夏だった。本当に暑かった。それは朝5時から、秋田では想像もできないような気温だった、という。あまりの暑さに、就寝の時だけ、エアコンの使用を許された。しかし、秋田ではエアコンなど“ハイカラ”な家電など普及していなかった時代。冷房にすべきことを、あろうことか、暖房のスイッチをオンにして床に就いた。もちろん、眠ることはできるはずもない。「廊下に出たら、本当に涼しかったことが懐かしい」と語る。
高校球児として最後の大会となったのは、栃木国体だった。安保は初戦となった広陵(広島)戦の7回表1死一、三塁という場面で、山内英雄(大洋・現DeNA)をリリーフした。春の全県大会での準決勝・金足農以来の登板は、文字通り、高校生活の最後の登板となった。この国体では投打がかみ合い、秋田商は準優勝に輝いた。
大学は日体大へ進んだ。本当は早大への憧れもあったが、「自分の力を考えての選択だった」という。また、秋田商から日体大へ進んだ秋田商の元監督・加藤肇のアドバイスがあったことも決め手となった。
日体大の野球部は、選手のほか審判、コーチ、トレーナーなどの部門に分かれ、部員は100人を超えていた。
安保は2年から試合に出場することができたが、東海大・高野光(ヤクルト)のボールに打線は沈黙、どうしても高野の壁を打ち破ることができなかった。しかし、4年になると1学年下の園川一美(ロッテ)との2枚看板で、首都リーグを制した。

大学時代は、その後、有名選手として活躍した多くの選手と対戦した。記憶に残っているのが、法大の小早川毅彦(広島)のありえない打球の速さと飛距離。これには驚いた。
大学へ入学した当初、「将来は高校野球の指導者にでも」といったような将来像を描いていた。そして卒業時、秋田県の教員採用試験を受験したが、たった1名の採用枠に100名以上が受験する、という競争率に合格することは叶わなかった。
そんな中、三菱自動車川崎から声が掛かった。当時の川崎市は社会人野球では日本一の激戦区。日本石油の山岡政志(秋田商出)、全日本のメンバー入りしている東芝には、三原昇と木村重太郎の下手投げの好投手がいたことから、安保は「下手投げ対策」としてアルバイトに行った縁での入社だった。
関西からの誘いもあったが、甲子園での「暑い経験」が脳裏をよぎり、関西での生活は無理と判断して、断った。
三菱自動車川崎では3シーズンで現役を退いた。高校時代に経験した腰痛に悩まされたのが、選手生活を縮めたのだった。そして秋田へ帰った。幸いなことに、会社からは2年間の出向扱いという厚遇扱いだった。
地元では当時、花輪高に親戚がいたことから、野球部の監督を引き受けることになった。6年間、監督を務めたが、出向扱いが切れた2年後、三菱自動車川崎と相談の結果、現在も務めている太平興業(株)に残る決断をしたのだった。
仕事と野球の監督を両立できたことに対して、「会社をはじめ、選手の父兄の協力に感謝したい」と語る。
花輪高の監督を務めた際に、一番気を配ったことは「(選手に)けがだけは絶対させないこと」だった。このことには細心の注意を払った。その背景には、特に3年最後の夏の大会は「ベストな状態で試合をさせたい」という“親心”があった。

秋田の野球については、「目標は常に高く設定して、取り組んでほしい」と語る。
「全国大会への出場程度の目標では、絶対出場することはできない。全国で勝ち進むためにも、『全国優勝』を目標にするくらいでないと、いけない」とアドバイスを送る。
さらに指導者には、選手以上に勉強なり、努力してほしいともいう。
「高校野球の監督は片手間でできるような、生ぬるいものではない。(県内の)現状を見渡すと、教員と監督を同時にこなしていることが大変すぎて、かわいそうになる。(県外の)強豪私立の高校ではないが、監督をサポートする人材の確保が急務ではないか」と現状に苦言を呈している。
安保にとって野球の存在はなんだろうか?
「今の自分があるのは、野球をやっていたからこそで、自分が進むべき道を切り開いてくれたのが、野球だと思っている。自分の人生をつくってくれた野球には本当に感謝している」と結んでくれた。

編集後記
どの時代も「一流のチームでエースになる実力はなかった」と自身が分析するように、必ず周囲には素晴らしい選手の存在があった。そのスペースに自分が生きる術(すべ)を確保し、切磋琢磨して実績を積み上げた姿に、さすが秋田商の一時代を築いた主将だ、と痛感した。高校から親元を離れて野球に取り組んだ安保さん。これまでの野球経験を通じて培ったスキル、精神面、取り組み方など、これからの秋田の野球界の発展のために尽力してほしいものだ。
≪文・写真:ボールパーク秋田編集部≫
~ profile ~
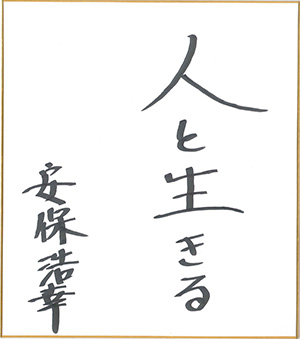 |
安保 浩幸(あんぼ ひろゆき)氏 |
|

